岡尾山 浄宗寺
阿戸の岡尾山浄宗寺は、浄土真宗本願寺派の寺で、現住職は第十五世釋徳水です。「芸藩通志」には、阿戸にある浄宗寺を岡尾山といい、もとは真言宗岡尾山養楽寺といっていたが、天正十三年(1585年)僧道順のとき、浄土真宗浄宗寺と改めた、と伝わっている。
また沼田町史には、浄宗寺は元亀元年(1570年)に道順が井田屋垣内に創立した岡尾山松元院養楽寺の後で、天正十三年大下に移転し、文禄三年(1594年)、一説によると、天正十三年真宗に改宗し、後に三代祐念のとき、明歴二年(1656年)現在地に移ったと伝えられているという記載がある。
また、親鸞聖人生誕八百年記念事業として、建てられた石碑には、次のような碑文がある。
「当山開基道順法師長門の武官この地に来たり大親町帝、元亀元年沙門となり道順と号す、同年廿才の春、中の地に一宇建立遍照院養楽寺と号し真言宗に属す。天正十三年大下の地に造営し改宗して浄土真宗に属す。第三第祐念明歴三年岡尾山に移り諸堂宇完備」
浄宗寺の建造物に関する古い記録によると、江戸時代の中ごろから、本堂・鐘撞堂・山門の再建の記録があり、明治二十年代には、本堂・向拝・後堂の大修復、大正年間に経蔵、昭和に入って、戦後鐘楼の新改築がなされている。
明治の大修復から百年を経、総工費約二億円の浄財でもって、平成九年から二年余りの歳月をかけ、「平成の大修復」がなされた。
本堂の前方移動、基礎工事、屋根組も寄棟から寝殿造り風に、内陣改装、炊事場、大手門の改築、山門の修復、便所の新設等大規模な工事であった。住職も十四世から十五世に継承。
しかし、古い彫刻や木組は、そのまま随所に残され、先人の優れた匠の技を目にすることができる。お念仏道場としての活用を願う。
仏教壮年会
仏教壮年会は、壮年層が、お寺に気軽にお参りし、日ごろから「お念仏相続」ができる環境を育て、浄土真宗のみ教えをいただくことが仏教壮年会の活動がもつ意義です。
こうしたことから、当仏教壮年会は、第1回目のスローガンとした「友と語り 仏と語る 仏壮会」を基調におきます。
平成30年度も「同朋の輪をひろげよう」をテーマに、法座、研修会、及び親睦会行事など各種活動を積極的に取り組むこととします。
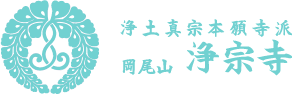

 昔からの文化も、人々のあたたかい心も揃った場所で、今年でおかげで65周年をむかえることが出来ました。50周年のときには記念として色々な行事をさせていただき、60周年の時には記念品を配布して園児、保育士、保護者、地域の人々に多くの思い出ができたこととおもいます。
昔からの文化も、人々のあたたかい心も揃った場所で、今年でおかげで65周年をむかえることが出来ました。50周年のときには記念として色々な行事をさせていただき、60周年の時には記念品を配布して園児、保育士、保護者、地域の人々に多くの思い出ができたこととおもいます。